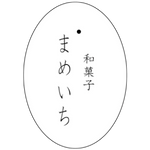今年も一年の半分が終わろうとしています。どんな半年でしたか?
飛翔の小道
露地とは、待合から茶室へと導く庭の小道のことです。飛び石や敷石に導かれるように進んで行くと、違う世界にいざなわれる感覚をおぼえます。
岡倉天心の茶の本は、露地とは自己の目覚めへの移行としての序章のようにとらえていています。千利休は、究極の孤独をめざして露地を作る極意を伝えています。小堀遠州は、ぼんやりとした夢の中をさまよいながらも新たな目覚めを迎えようとしている魂の状態として、露地の着想の句を残しています。
夏の木立の茂み
海が垣間見える
淡い夕月
夏の木立。異世界への敷石。いざなわれる不思議をイメージしてみました。黒糖わらび餅入り合わせあんのこなし製です
原材料:大手芒 砂糖 黒糖 わらび粉 小豆 きなこ 米粉 餅粉 寒天 ほうれん草 ビーツ /金箔
八陣の庭
作庭の名手として名高い小堀遠州の代表作、二条城二の丸庭園。どの方向からも素晴らしい眺望が得られるように作庭されたこの庭園は、八方から眺められるという意味を込め、またそれを中国三国時代の知将である諸葛孔明(しょかつこうめい)が考案した八陣に例え、「八陣の庭」と名付けられました。庭園の中心を担う池には蓬莱島という名の中島が浮かんでおり、その左右に長寿のシンボルである鶴と亀をそれぞれ模した鶴島と亀島が配置されています。これらは大陸より伝わった神仙蓬莱思想を表したもので、池を海、島を仙人の住む蓬莱山と見立てることで、永遠なる繁栄の願いを表しているのだそうです。蓬莱島の石組みは、どの方向から見ても常に鶴と亀が対を成すよう工夫されています。
遠州が茶人でもあったことから、緑茶をベースに、エルダーフラワーシロップとレモンで爽やかに仕上げた錦玉羹を池に見立て、粒餡と緑豆餡に抹茶パウダーをまぶして3つの島を表現しました。
手の平サイズのお庭を是非ご堪能ください。
作.千葉瑞葵
原材料:緑豆 砂糖 小豆 緑茶 エルダーフラワー レモン 抹茶 水あめ 寒天
雨手鞠
宇治市の三室戸寺。四季折々の花が楽しめるお寺があり、特に「あじさい寺」として有名です。あじさい園は山門の右手側に広がる「与楽苑」内にあります。与楽苑は、平成元年(1989)に「昭和の小堀遠州」ともいわれる作庭家・中根金作が手がけた、約5,000坪の広大な庭園です。見頃を迎える6月には拝観者で賑わい、紫陽花ライトアップや“ハートの紫陽花”も話題のお寺です。私にとって京都修行時代に母と行った思い出の場所です♡
カルピス羊羹にローズヒップハイビスカスとバタフライピーのハーブの錦玉羹で、雨に遊ぶ紫陽花をイメージしてみました。
こちらの和菓子は、イラストレーター舘野明日佳さんの2025カレンダーに素敵に描いていただいています♪
原材料:大手芒 砂糖 カルピス レモン ローズヒップハイビスカス バタフライピー 水あめ 寒天
元気餅
~和菓子の日の行事菓子~
和菓子の日の行事菓子がないのなら作りましょう!ということで、まめいちが考案しました。平安時代、16個の餅や菓子をお供えするところからはじまった行事。江戸時代は「1」+「6」で7つの菓子、七嘉祥に姿を変えました。令和の時代は、7つの食材を1つの菓子に込めまして現代人に合うように栄養たっぷり調整いたしました。
腸の調子を整える味噌、疲労回復のクエン酸の梅干し、食物繊維やタンパク質ビタミン、鉄分と栄養バランスの優れた小豆、粘膜の健康維持のためのβ-カロテン豊富な大葉、良質な脂質と旨みが濃厚な金ごま、ビタミン・ミネラル・アミノ酸豊富なかつお節と免疫力強化の青のりをまぶしました。
「一個食べれば 元気になる 元気餅!」
原材料:大手芒 砂糖 大納言かのこ豆 道明寺 仙台みそ 大葉 かつお節 梅 金ごま 青のり
水無月
~6月30日夏越の祓 行事菓子~
一年のちょうど半分にあたるこの日。半年生きてきて、何気なく犯してきた罪や穢れを祓い、年末大晦日までまた元気に明るく過ごせるように身を清める行事です。日本神話のスサノオノミコトに由来する風習で、茅(ちがや)という草で編んだ直径数メートルの輪をくぐる茅の輪くぐりが執り行われます。その行事菓子が「水無月」です。
三角形の氷に見立てた外郎に、邪気を祓うという意味が込められた小豆の甘納豆をたっぷりとしきつめたもちもちとした和菓子です。
原材料:小麦粉 砂糖 小豆 上用粉 浮き粉
今月のテーマは京菓子展
毎年、京都・有斐斎弘道館で開催されます『京菓子展』の今年のテーマが発表されました!去年は、時間切れで提出を断念しましたので、今年こそは!8月末が提出期日だと思われますので、7月末を私の中の提出期日にすれば、必ず間に合う!という事で、とことん調べて行きます☆彡
『小堀遠州と松花堂昭乗』小堀遠州さんはなんとなく耳にしたことあるけど、松花堂さんの方は、豪華な弁当という事しかわからないーーー!
なんでこのふたりなの?ふたりはどんな関係?何をした人?どんな人?
小堀遠州さん。近江小室藩主(1万2千石)で江戸初期の大名茶人です。大名茶人とは、領主でありながら茶の湯を熱心に学び普及発展に尽力した人の事を言います。幼少の頃より父新介正次の英才教育を受け、千利休、古田織部と続いた茶道の本流を受け継ぎ、徳川将軍家の茶道指南役となります。 書画、和歌にもすぐれ、王朝文化の理念と茶道を結びつけ、「綺麗さび」という幽玄・有心(「幽玄」とはもともと中国の仏教思想で教義の奥深さのこと。「有心」は文字通り無心の反対。つまり「深い心がある」という意味です。)の茶道を創り上げました。遠州は、後水尾天皇をはじめとする寛永文化サロンの中心人物となり、また作事奉行として桂離宮、仙洞御所、二条城、名古屋城などの建築・造園にも才能を発揮しました。
松花堂昭乗さん。慶長5年(1600)石清水八幡宮の社僧真言宗の僧侶です。次いで瀧本坊の住職となりました。昭乗は、書道、絵画、茶道の奥義を極め、近衛信尹、本阿弥光悦とともに寛永の三筆と称せられ、独自の松花堂流という書風を編みだしました。
【ふたりの出会い】小堀遠州の正室の妹が、中沼左京元知の妻となったことでその左京の実弟であった松花堂昭乗。そこでふたりの交流が始まります。松花堂昭乗は小堀遠州から茶道を学び、強く影響を受けたと言われています。このふたりの働きは平和な政治の下地となったと言われています。そしてとっても仲良し♪気が合ったのですね。
【空中茶室を夢みた男】小堀遠州は城づくりに全国飛び回り忙しい毎日。松花堂昭乗は八幡宮と幕府の橋渡し役でストレスのあるお勤め。そんなふたりが夢見たのは、『絶景を見ながら美味しいお茶が味わえたら最高だろうに!私たちにはそれができるんでは!』と、高さ7mの懸け造り(清水寺のような建物のイメージです!)空中茶室。雲に浮かんでいるような茶室『閑雲軒かんうんけん』を作っちゃいました!!千利休の「侘び寂び」に、江戸の華やかさをほんのりと重ねた「綺麗さび」なデザインが加わった茶室には、最先端の文化サロンとしてたくさんの文化人が集う場所となったそうです。
わたくし、まめいちは 3D8K茶室を夢見る女。時空を超えて、どうやらマッチングしてしまったようです
京菓子展大賞目指して、鼻息荒く挑みます!皆さま!応援よろしくお願いします(*´▽`*)!